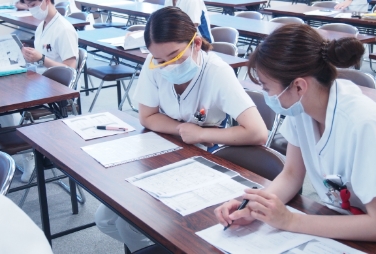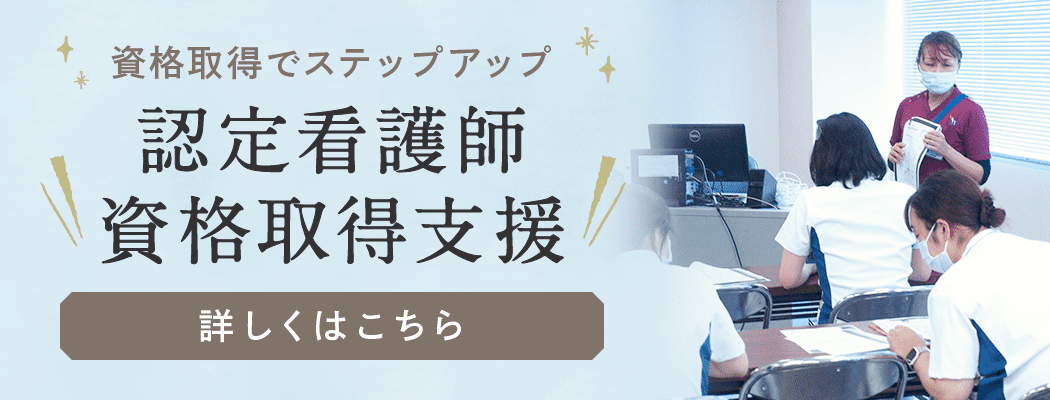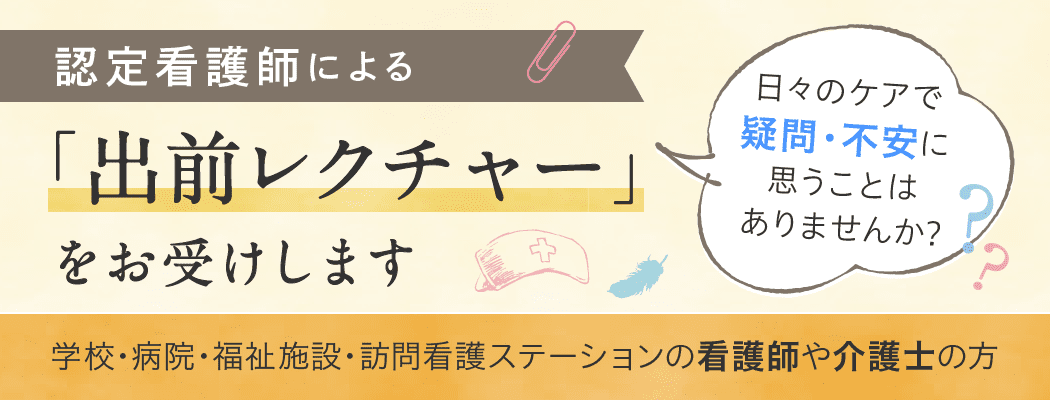認定・特定行為看護師のご紹介


社会医療法人清恵会では、日本看護協会が認定する資格「認定看護師」の取得をバックアップ。資格取得に関わる研修受講費用を支援。
各専門教育機関での学習中は給与を支給するなど、資格へのチャレンジをサポートしています。
クリティカルケア認定看護師・特定行為看護師
活動内容
- 一次救命処置(BLS)講習会での指導
- 病院内二次救命処置(ACLS)講習会での指導
- フィジカルアセスメント研修
- 褥救急外来受診者への対応およびスタッフへの指導
- 災害対策 , e t c .

フィジカルアセスメント研修
フィジカルアセスメント研修では、ラダーの集合研修で事例を作成し、シミュレーターなどを用いたフィジカルアセスメントや臨床判断を行う研修会を開催しています。

中西 紀彦 清恵会病院 救急医療センター 副センター長
クリティカルケア部門とは、生命が危険にさらされている状態や重篤な疾患を抱える患者さんを専門的に治療・ケアする医療分野のことを指します。この分野においては、個人・家族および集団に対して高い臨床推論能力と病態判断能力に基づき、熟練した看護技術ならびに知識を用いて水準の高い看護を実践できることが求められます。
感染管理認定看護師
活動内容
- ICT[感染対策チーム]ラウンド(1回/週)
- AST[感染対策チーム]ラウンド(1回/週)
- 院内感染防止委員会への参加(1回/月)
- 看護部感染防止委員会の開催(1回/月)
- スタッフへの感染拡大防止対策指導
- 職員研修の開催、職員への指導
- サーベイランス(感染症に対する調査・監視)の実施

感染対策ラウンド(ICT、AST)
医師、看護師、薬剤師、検査技師と各専門家の意見をもとに、ICTでは感染対策の実際、ASTでは感染症治療の評価を実施し、総合的な感染対策向上に努めています。

小川 恵子 清恵会病院 感染対策室
感染管理認定看護師の役割は、人々を感染から守ること。守る対象は、患者さんをはじめ院内の全スタッフ、お見舞いに来られる方、病院に出入りする関係者まで、すべての人々です。各診療とも連携して院内全体をトータルに管理し、安全で快適な医療環境をつくります。
皮膚・排泄ケア認定看護師
活動内容
- 褥瘡回診(2回/週)
- ストーマ外来(1回/週)
- 職員研修の開催、職員への指導
- 褥瘡発生率、保有率のデータ収集
- 地域の訪問看護ステーションからの相談

ストーマ外来
ストーマ(人工肛門・人工膀胱)を保有する方々が、ストーマと共に快適な生活を送れるように支援を行っています。退院後の生活に合わせ、ストーマ装具の悩みやスキントラブル予防について手助けさせていただきます。

山本 史絵 清恵会病院 医療安全対策室
創傷、ストーマケア、失禁ケアに対し専門的なケアを提供する看護師です。褥瘡や創傷のケア方法の検討、オストメイトが安心して生活できるように外来での関わり、失禁によるスキントラブルへの対応を行っています。その人らしく過ごすにはどうすればよいかを考え、活動しています。
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師
活動内容
- NST[栄養サポートチーム]委員会への参加(1回/月)
- NST[栄養サポートチーム]ラウンド(1回/月)
- 脳外科回診の参加
- 職員研修の開催、職員への指導

脳外科回診
脳外科回診で現在の離床や覚醒状況を把握し、他職種と相談を行い嚥下機能や高次脳機能の改善に向けた看護を提供できるようにしています。

又吉 由加里 清恵会病院 3B病棟
脳卒中患者さんの急性期から病態の重篤回避のためのモニタリングを行い、機能障害に対してADL拡大のために早期リハビリテーションを実践します。また障害に応じて自立支援の為に他職種と協働行うことや再発予防の健康管理など患者さんやご家族に対しての指導をする役割があります。
慢性呼吸器疾患看護認定看護師
活動内容
- RST(呼吸サポートチーム)ラウンド(1回/週)
- 呼吸リハビリ回診(1回/週)
- 看護外来(1回/月)
- 在宅酸素療法指導(入院・外来患者さん)
- 呼吸ケアセミナーの開催(7回/年)
- 職員研修の開催、職員の指導
- 多職種からの呼吸ケアに関する相談対応

RSTラウンド
RSTラウンドでは多職種が集まり多方面から呼吸ケアのサポートを行い、また呼吸ケアに関する講習会を開催し、呼吸ケアの質の向上に取り組んでいます。

中岡 真実 清恵会病院 4B病棟
慢性閉塞性肺疾患や間質性肺炎などの慢性呼吸器疾患は、悪化と寛解を繰り返し緩徐に進行していきます。呼吸器疾患患者さんは生涯にわたり病気とともに生活をしていく必要があります。様々なことと折り合いをつけながら、その人らしい生活を送ることができるよう支援していきます。